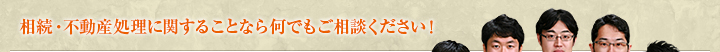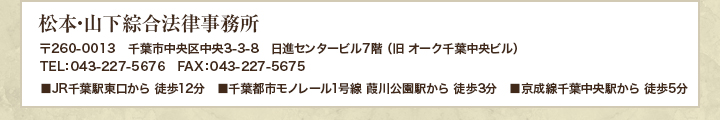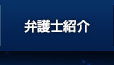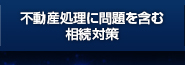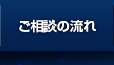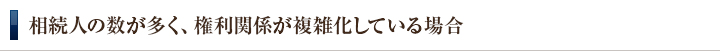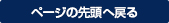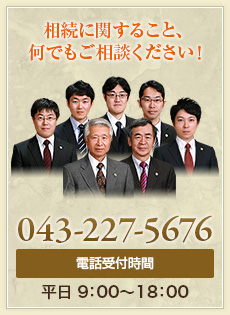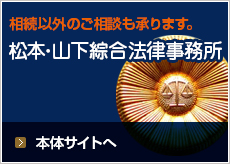多数の不動産がある場合は、通常課税問題を考えなければなりません。
預貯金等の流動資産が多ければ問題ありませんが、不動産の比重が高い場合は売却、あるいは物納できる不動産を確保する必要があります。売却は早期にしなければならないため価格が低くなることがあります。また、物納は基準が厳しくなっているため「物納でいいか」というわけに行きません。できれば相続開始前に計画的な財産管理が必要です。
自宅を含め2、3の不動産が遺産の中心である場合には相続人間の調整が問題です。不動産を希望する相続人が多い場合や、だれもいらないという逆の場合もあります。
被相続人が遺言で、遺産の承継についてその意思を表示しておくことで紛争を予防する効果が見込まれると言えます。

相続財産である不動産に相続人の一部が居住している場合はよくあります。
可能であれば当該不動産は居住者が取得することが問題を少なくしますが、外の相続人を満足させられるかの問題が生じます。当該不動産の評価が高く、他にめぼしい遺産がない場合には紛争を大きくします。
被相続人が遺言を作成しておく必要が高い場合といえます。
住宅ローンについては、被相続人が通常は団体生命保険に加入していて、死亡時の生命保険で完済される場合が多いと思います。従って、資産のみの相続となる場合が通常です。
住宅ローンが残った場合には残金は相続債務となりますので、相続税の関係では差し引かれますが相続債務である住宅ローンは相続分に分割されて各相続人が相続することになります。通常は、当該不動産を承継する人が残債務を引き受け金融機関と新たな契約を結んで外の相続人の債務が残らないようにしなければなりません。
最近は少なくなりましたが、相続人が多い事例は紛争の解決が困難な事例といえます。
相続人が増えるほど、各個人の個性や生活状況等で希望や要求が多様化し、簡単に合意できません。
ことに、被相続人の次の世代が亡くなり「孫の時代」の相続となると、数も増え、また色々な生活歴の人が参加するため、話し合いが難しいのが実情です。
この様な場合は裁判所の手続(調停・審判)の利用がどうしても必要になる事例といえます。